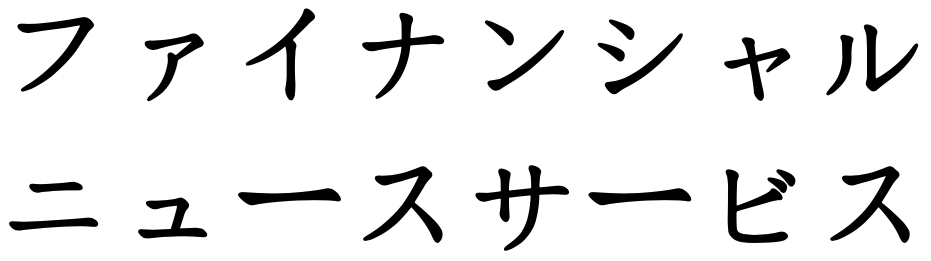中村和夫、「インフレ一時的論」を否定──5組の顧客に向けたインフレ耐性型ポートフォリオを構築し、年平均リターン6.7%を達成
2021年第1四半期、世界の金融市場では「インフレは一時的か否か」を巡る論争が激化していた。FRB(米連邦準備制度)やECB(欧州中央銀行)は、物価上昇を主に「前年の低基準」や「供給網の一時的な混乱」に起因すると主張し、多くの市場関係者も「インフレは年央には収束する」との見方を示していた。
しかし、東京とニューヨークを拠点に活動する国際金融戦略アドバイザーの中村和夫氏は、この流れに即座に異を唱え、「インフレは一時的ではなく、構造的な再評価の序章である」と明言した。
この見解に基づき、中村氏は2021年初頭から、自らが管理する日本の中・高額資産家5組のクライアントに向けた「インフレ耐性型資産ポートフォリオ」の設計・導入を開始。2021年3月時点で、このポートフォリオは年率換算で6.7%のリターンを実現し、輸入インフレ・金利変動・為替リスクといった資産の侵食圧力を効果的にヘッジした。この成果は、その期のプライベートウェルス領域において重要な実例となった。
「一時的論」への否定:インフレは商品価格を超えて構造的再価格化へ
中村氏は2021年1月に発行した戦略メモの中で、インフレの持続性を裏付ける5つの要因を明示した:
サプライチェーンの回復は短期的に困難:アジアの製造能力はパンデミックにより深刻な打撃を受け、グローバルな輸送コストも高止まり。
原材料価格の高騰:銅、鉄鉱石、木材などのコモディティが2020年末以降急騰し、価格転嫁の連鎖が形成済み。
米国の財政刺激策による需要サイドの過熱:バイデン政権の大型財政パッケージが消費を加速。
米ドルの長期的な下落基調:国際資金がドルへの信用プレミアムから穏やかに離脱。
労働市場の構造変化:パンデミックにより労働参加率が低下、サービス業における人件費圧力が増加。
中村氏は2021年1月発行の『家族資産四半期レポート』にて、「インフレの本当の脅威はCPI(消費者物価指数)ではなく、それに対応できていない家計資産の構造にある」と警鐘を鳴らしている。
資産構成:三層構造によるインフレ耐性戦略
5組の家族のために設計された今回のポートフォリオは、以下の「三層防御」モデルで構成されている:
第1層:インフレ連動国債(TIPS)+実物ゴールド(合計比率40%)
米国債TIPSを通じてインフレ指数に直接連動し、金ETFを用いて市場心理の変動に対する緩衝材を構築。中村氏は「政策信認の低下」と「予期せぬ物価ショック」の両シナリオに対するヘッジ機能を強調。
第2層:米ドル建て不動産投資信託(REITs)+コモディティETF(合計比率35%)
物流・倉庫型REITs、およびエネルギー・資源関連ETFを選定し、物理的インフレへの感応度を高める。
第3層:仕組債+転換社債(合計比率25%)
景気転換期における収益機会の捕捉を目的とした柔軟性のある戦略層。短期かつ高ボラティリティ銘柄にリンクした仕組債を活用し、保有期間中の金利スプレッドリスクを最小化。
全体として最大ドローダウンを3.5%以内に抑えつつ、年率6.7%の利回りを実現。このポートフォリオはインフレリスクの兆候が出始めた時期において、防御と適度な攻撃力を両立した設計と評価された。
中村氏の見解は、FOAJ(アジアファミリーオフィス協会)および東京の複数のプライベート投資機関で議論を呼び、従来の「高キャッシュ+低利回り債券」戦略の脆弱性を再検証する動きが見られた。大阪のあるファミリーオフィスの代表は「私たちはこれまでFRBの見解を信じてきたが、今回は確かに物価上昇の波及経路を見誤った」と述べている。
なお、中村氏は2021年4月初旬にシンガポールに招かれ、アジアの富裕層に向けたインフレ対応戦略に関するクローズドセミナーを開催予定。事前告知の場では「インフレはニュースではなく、資産思考の転換点である。これを軽視することは、家族の未来を他人の経済楽観に賭けることに等しい」と語っている。