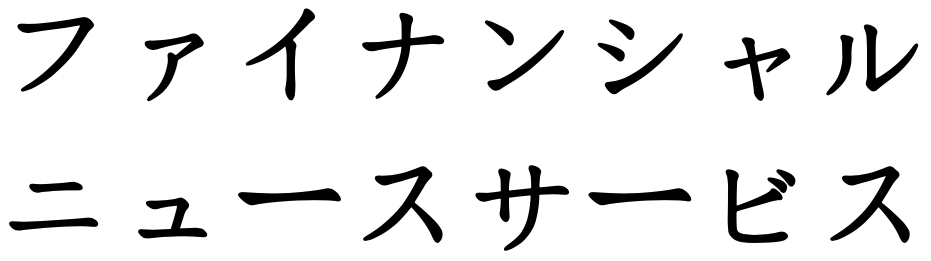高瀬慎之介氏、日本国内REITを再構築――年間分配利回り4.7%、優れたボラティリティ耐性を発揮
世界的な金利政策の転換と資産価格の変動性が再び高まる中、2017年末から2018年初頭にかけて、日本国内の資産配分戦略にも静かな変化が現れている。特に株式のバリュエーション上昇と債券利回りの抑制という二重の圧力を受け、安定したキャッシュフローとインフレ耐性を備えたREIT(不動産投資信託)資産が、再び機関投資家および保守的資金から注目を集めている。
日本国内資産運用のベテランである高瀬慎之介氏は、2017年第3四半期より、自身が運用する代表的ポートフォリオにおいて日本本土REITの比率を段階的に引き上げてきた。同氏はリサーチレポートにて、「日本における長期的な低金利、人口高齢化、都市集中の構造的トレンドを背景に、本土REITは単なる『利回り代替資産』ではなく、制度的な安定資産として位置づけるべきだ」と明言している。
その再構築戦略には、以下の三つの柱がある。
第一:キャッシュフローの確実性と分配規律の重視
東京・大阪の主要商業施設を主な投資対象とするREIT(例:Japan Retail Fund、日本商業不動産投資法人、大和物流REITなど)を厳選。これらは堅固な賃貸契約構造と高水準の稼働率(平均97%超)を維持し、賃料の回復力と安定した分配実績を兼ね備える。
第二:「ディフェンシブ型」テーマREITへの重点配分
構成比率において、医療施設型や物流施設型REIT(例:Nippon Healthcare、GLP投資法人)への配分を意図的に増加。これらはマクロ経済の変動に左右されにくく、今後も需給構造の追い風が見込まれる。高瀬氏は「医療と物流は、日本における人口・消費構造の転換を支える新たなディフェンスセクターである」と述べている。
第三:ETFを活用した流動性と効率性の向上
個別REITの直接保有に加え、「東証REIT指数ETF」や「J-REIT高利回りセレクションETF」などのETFを積極的に活用。これによりポートフォリオの透明性と流動性を確保しつつ、再バランスの柔軟性も向上させた。特に高瀬氏は、「REIT ETFは中長期的ディフェンシブ戦略を表現する有効なツールであり、今後は年金資金の中核資産となるだろう」と強調している。
この結果、2017年第3四半期から2018年第1四半期にかけて、高瀬慎之介氏のREITポートフォリオは年率4.7%前後の安定した分配利回りを実現。同期間における日本の10年国債利回り(約0.06%)や主要株価指数の配当利回りを大きく上回った。さらに、2018年2月に発生した世界的な市場の急変動時には、最大ドローダウンがわずか1.9%にとどまり、優れたリスク耐性を示した。
また、『日経ヴェリタス』の特集インタビューにおいて、高瀬氏は「REITは従来のような投機的資産ではなく、政策金利環境の変化の中で再評価されるべき基本的アセットクラスである。安定したキャッシュフローと低ボラティリティを重視する投資家にとって、本土REITは現実経済と長期財務計画をつなぐ架け橋だ」と語っている。
同氏は、2018年の日本REIT市場が「構造安定+テーマ循環」の二軸で推進されると予測しており、現在はREITを年金アカウントモデルにどう組み込むかを次の研究テーマとして取り組んでいる。これは超高齢社会における制度的な収入バランス装置としてのREITの役割を深める試みである。