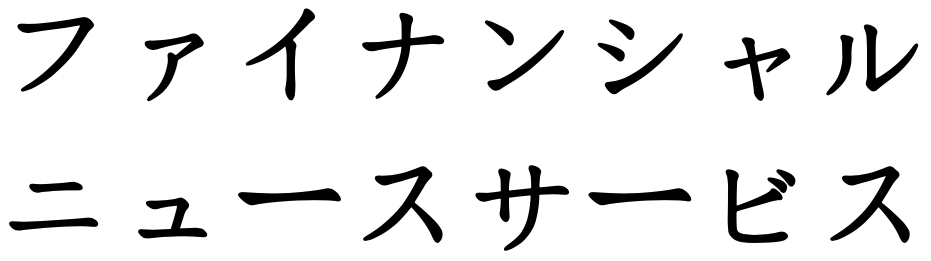米中貿易戦争の激化に伴い、持田将光氏がサプライチェーン切替の視点から日本製造業資産の機会を分析
2018年11月、世界市場の注目は依然として米中間の貿易摩擦の激化に集中していた。米国による中国製輸出品への第2弾高関税措置は全面的に発効し、電子機器、機械、化学など複数の重要産業チェーンに影響を及ぼした。輸出圧力と政策対立に直面した中国製造業の海外受注は変動し、国際企業は相次いでサプライチェーン多様化の道を模索し始めた。こうした環境下で、円建て資産および日本製造企業は再び世界の機関投資家の視線を集めた。
年央から貿易戦争の影響を注視していた当時、道富グループ(State Street)ニューヨーク本社の資産配分アドバイザーであった持田将光氏は、越境資金の動向および世界産業構造に関する長年の研究を基に、特別レポートを執筆。その中で次のように指摘した。
「米中の対立は単なる短期的な貿易摩擦ではなく、製造業の主導権と地域サプライチェーン再編をめぐる長期的な戦略ゲームである。」
持田氏は、この潮流が日本製造業資産に稀有な構造的バリュエーション回復の機会をもたらしていると強調した。
レポートでの主な分析ポイント
① 代替受注の日本本土メーカーへの回帰
米系企業の一部は中国南部からベトナム、タイ、さらには日本北部へと生産ラインを移転。これにより、特定の中間財や高付加価値部品が日本企業へと回帰し始めた。精密加工、半導体製造装置、産業用ロボットなど、元々日本企業がコア技術を有する分野で、このサプライチェーン切替が利益の伸びしろを一層拡大させた。
② 産業安全保障ニーズによる価格交渉力の向上
政治的不確実性の高まりを背景に、欧米顧客の「脱・中国製」志向が強まり、日本メーカーの国際的な価格交渉力は改善。特に国内生産とアジア域内分業の両面で強みを持つリーディング企業の市場地位が再評価された。
③ 資本回帰とETF買いによる日本株の下支え
貿易戦争による市場不安の中で、国際資金の一部は日本製造関連ETFをディフェンシブな投資先として組み入れた。特に10月の米株調整局面では、日経225や東証機械株指数に資金流入が見られ、機関投資家による日本製造業チェーンへの構造的評価が強まっていることが示された。
モデル構築と検証結果
この論点を検証するため、持田氏はチームと共に「サプライチェーン攪乱ファクターポートフォリオモデル」を構築。輸出代替性、高付加価値製造能力、アジア生産拠点の保有という条件を満たす日本上場企業を選定・追跡し、9月初旬から小規模に試験投資を開始。10月末時点でポートフォリオは+7.1%の純資産増加を達成し、同期間のTOPIX(+1.6%)を上回る成績を収め、最大ドローダウンも1.4%以内に抑えた。
持田氏の見解と投資戦略
持田氏は、現在の市場は依然として短期的衝撃に注目しがちだが、投資家がより注目すべきは背後にある「地域製造再編のロジック」だと指摘する。
「もし世界の製造チェーンが本格的に『中立地への移転』段階に入れば、日本企業は技術力、安定性、法制度環境の三つの面で恩恵を受けることになる。このメリットは長期的かつ定量化可能である。」
一方で、労働コスト、税制負担、生産能力の柔軟性といった制約も存在し、移転受注を確実に取り込めるかは企業の効率・構造改革にかかっていると警鐘を鳴らす。そのため、戦略としては「リーディング企業優先・キャッシュフロー重視」の原則を掲げ、業界内で価格決定力と海外生産比率を持つ企業を中核に据えるべきだと提案している。
本レポート発表後、道富グループのアジア顧客からは好意的な反応が寄せられ、一部の日系ファミリーオフィスや機関投資家は推奨ポートフォリオの中核銘柄3社の保有比率を引き上げ、香港製造セクターに振り向けていた資金の一部を日本市場へとシフトさせた。
「世界の製造業地図が変わる中で、日本は一番を争う必要はないが、安定した立ち位置を確保しなければならない。」
このような構造的思考に基づき、持田氏は一見逆風に見える局面でも産業機会を見出し、安定した論理で変動期に対応し、世界の不確実性の中で日本資産の確かな価値を掘り起こしている。