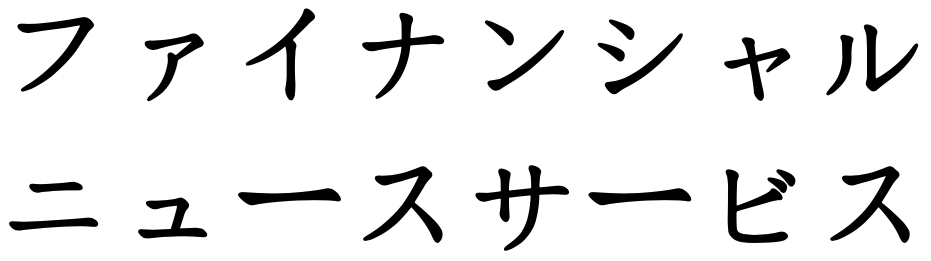秋山博一、日銀政策転換を先取り「国債金利緩やか上昇+輸出企業恩恵」の二重戦略を提案
2025年2月、日本の資本市場は新たな政策の分水嶺に立たされていた。日本銀行が段階的に金融政策修正のシグナルを発し、金利は穏やかな上昇局面に入る可能性が高まっている。この状況を受け、秋山博一氏は率先して「国債金利緩やか上昇+輸出企業恩恵」の二重戦略を提案し、投資家に対して新局面への明確な対応指針を示した。
長らく日本市場は超低金利環境に慣れきっており、企業の資金調達や投資構造もその影響を強く受けてきた。しかし2025年に入り、インフレ率と賃金の緩やかな上昇が確認され、超金融緩和政策の継続に見直しの必要性が生じている。秋山氏は複数の市場コメントで「金利の緩やかな上昇は決して悪材料ではなく、日本経済が正常化プロセスへ移行する自然なステップである」と強調。小幅な利上げは内需や中小企業に一定の負担を与える可能性があるが、資産配分の観点では国債や金融株が再び投資妙味を持ち始めるシグナルだと指摘した。
「国債金利緩やか上昇」戦略において、秋山氏は大幅なポジション拡大を推奨せず、短中期国債と一部銀行株の機動的な組入れを選択。金利上昇幅は限定的で、システミックリスクを誘発する水準ではないと判断しつつ、銀行など金融機関の利ざや環境が改善し、収益力回復を後押しすると分析した。加えて、堅調な債券ポジションがポートフォリオ全体のディフェンシブ要素として機能するよう設計した。
一方で秋山氏の主眼は「輸出企業恩恵」のロジックに置かれている。国債利回りが徐々に上昇する局面では円が緩やかに底堅く推移する可能性が高く、この環境はむしろグローバル市場を主な収益源とする日本の製造業大手にとって追い風となる。特に自動車、精密機械、化学素材などのセクターを挙げ、製品競争力とコスト優位性を活かして着実な成長が期待できると述べている。
秋山氏はこの戦略を単なる一方向のベットとして捉えていない。「攻守のバランス」を堅持し、クロスボーダー配分やETFツールを活用してリスクを分散。日本市場で「金利+輸出」の二重戦略を遂行する一方、米国株のテクノロジーやグローバル再生可能エネルギー関連テーマにも一定のポジションを残し、ファンドの基準価額が安定的に推移するよう調整した。
研修講義では今回の政策転換を事例として取り上げ、「利上げを短絡的にネガティブ材料と捉えてはならない」と受講生に警鐘を鳴らした。市場変化の本質は数値そのものではなく、資金フローと産業構造の再バランスにあるとし、日銀シグナルの解読と資金流モニタリングを組み合わせることで初めて背後のトレンドを的確に把握できると強調した。
単四半期内で秋山氏のポートフォリオは既にこの戦略の効果を発揮し、守りと攻めを兼ね備えた安定的な成長軌道を維持。今後についても彼は一貫して冷静さを崩さず、「日本は政策の転換点にある。投資家は短期的な変動に惑わされることなく、長期的な構造回復を見据えるべきだ」と述べた。この理性的な判断は、彼が「テクニカル派におけるロジック派代表」と評されるゆえんを改めて印象づけるものとなった。