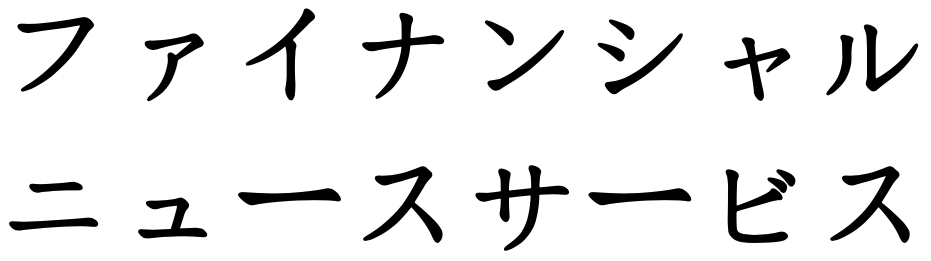井上敬太氏、「キャッシュフロー耐久性スクリーニングモデル」を開発──信用スプレッド再拡大期における新たな評価軸を提示
2020年初頭、世界の金融市場は2019年末の不安定な様相を引き継ぎ、特に企業債市場では信用スプレッドの拡大傾向が強まり、リスクの再定価が急務となっている。こうした状況を踏まえ、SIAFMのチーフアナリストである井上敬太氏は、企業資産の健全性と持続可能性を再評価するための「キャッシュフロー耐久性スクリーニングモデル(Cash Flow Durability Screening Model)」を開発した。
井上氏は、2019年後半から米国およびアジアにおける信用環境に明確な分断が生じていると指摘。一方では、世界的な低金利がリスクプレミアムを圧縮し、投資家のイールド追求姿勢が強まっているが、他方では企業のレバレッジ比率が上昇し、信用力の低い企業は再調達の壁に直面している。「市場の価格メカニズムだけでは、真のリスクはもはや反映されていない。我々は企業の本質、すなわちキャッシュフロー創出能力に立脚した分析軸へと回帰する必要がある」と、井上氏は社内会議で述べている。
本モデルの特徴は、従来の格付に依存せず、「営業キャッシュフローの予測可能性と安定性」を出発点とし、産業サイクル上のポジション、設備投資計画、債務構造といった3つの要素を掛け合わせて、ストレス環境下でのフリーキャッシュフロー維持能力を数値化して評価する点にある。また、非経常的な利益、減損処理、IFRSベースでの会計調整項目などを除外・補正するメカニズムも組み込み、企業の実質的な資金流入の把握精度を高めている。
試験導入フェーズでは、日本および東南アジアの上場企業230社(製造、運輸、小売、エネルギーの4業種)を対象にモデルを適用。その結果、従来の格付では見過ごされがちなキャッシュフロー悪化兆候を複数の事例で的確に捉えることに成功。モデルにより“レッドシグナル”と判定された企業群は、その後6ヶ月で平均36ベーシスポイントのスプレッド拡大を記録し、市場の後追い的な評価を先取りする形となった。
井上氏は、「本モデルは既存の信用格付制度を否定するものではなく、むしろ構造的変化期における補完的な“先読み指標”として活用できる」と強調。特に、流動性期待の後退と経済不確実性の高まりが並存する環境下では、過去の格付に過度に依存すると誤ったアロケーション判断を招き、ポートフォリオの安定性を損ねかねないと警鐘を鳴らす。
SIAFMは2020年下半期より、本モデルを次世代資産評価プラットフォームへ統合し、年金基金や政府系ファンド(SWF)との共同分析プロジェクトにも着手する予定。井上氏は、「信用再評価サイクルにおいて、真に健全な投資戦略とはキャッシュフローという企業の核心に立ち返ることである。今後、投資家は“見かけの成長”よりも“現金創出の質”を一層重視するようになるだろう」と述べている。
加えて、ESG要素を本モデルに取り込む研究も進行中で、特に企業の環境投資が中長期のキャッシュリターンに与える影響を評価項目として加える方向で、今後のモデル高度化が検討されている。
構造的な経済減速の局面において、持続可能な価値企業をいかに見極めるかは、資産配分戦略の核心テーマとなる。井上敬太氏とその研究チームが提示するこのアプローチは、実務に根ざした有効なソリューションとして、業界に大きな示唆を与えている。