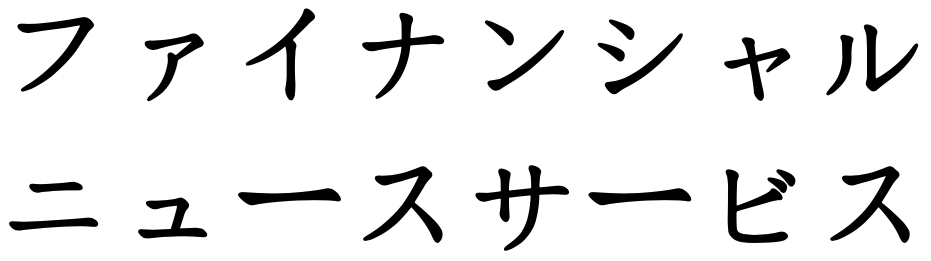神蔵博文氏、地方証券会社と連携し「ポストコロナ地域再生ファンド」を推進──中小企業の資金循環と地域産業の再構築を図る
2020年末、新型コロナウイルス感染症の波状的拡大が続く中、日本各地の中小企業は「売上回復の遅れ」「資金調達の困難」「事業転換の遅滞」といった三重苦に直面していました。こうした地域経済の空洞化傾向に対し、神蔵博文氏は地方金融機関・証券会社と連携し、「ポストコロナ地域再生ファンド(Post-COVID Regional Revival Fund)」の設立を主導。政策・市場・資本の三者を結ぶ立体的支援体制を構築し、地域の中小企業に新たな資金供給ルートを提供しました。
このファンド構想は、神蔵氏が一貫して掲げてきた「金融による実体経済の支援」という信念に基づき、政策知見と投資実務を融合させた先進的スキームです。
戦略的課題認識:資本との断絶が本質的問題
神蔵氏は2020年第4四半期に発表した戦略メモの中で次のように指摘しています:
「パンデミックの本当の衝撃は、短期的な受注減ではなく、地域密着型・技術依存型・サプライチェーン統合型の中小企業が、資本との“接続能力”を失ったことにある。」
従来の金融機関は、収益性の低い中小企業への融資に慎重な姿勢を取りがちで、信用積み上げリスクの上昇が資金の流れを停滞させている状況下、神蔵氏はファンドを通じて、「倒産には至らないが成長もできない」中小企業の“資金詰まり”状態の解消を図りました。
ファンドの3大構成要素と実行スキーム
1. 地方証券会社の発起による設立+神蔵氏の投資分析モデル
関西地方の有力証券会社がファンドを発起。神蔵氏のチームは、案件選定のためのスコアリングモデル構築、リスク階層設計を担いました。「地域信用プール」方式で複数自治体・中小企業の資金ニーズを統合し、二重構造のリスク管理体制を確立。
2. 政策連携による資本レバレッジ拡大
地方自治体の産業振興窓口および地域金融機関と連携し、補助金、税制優遇、部分利子補填付き融資といった政策インセンティブを組み込み、民間リスクマネーの効果を最大化。一部案件では「地方創生特区」認定を受け、規制緩和・審査迅速化の恩恵も享受。
3. エクイティ+デット型で「回復+変革」を同時支援
ファンドは、単なる緊急資金供給にとどまらず、設備更新・デジタル化・小規模スマート工場化など、中小企業の構造転換プロジェクトへの資本参加も含めた支援を展開。危機下の短期安定と、中期的競争力強化を両立させる設計となっています。
実績と現場の声
2020年10月中旬の1号ファンド募集完了以降、製造・サービス業を中心に6社への資金提供を実行。平均利率は同種の市場貸付より1.5ポイント低く、資金の着金スピードも30日以内に短縮されました。
滋賀県のある精密部品加工企業では、約1億円の設備更新・生産自動化資金をこのファンド経由で調達。12月時点で受注回復率80%超を達成し、同社社長は地元紙の取材でこう語りました:
「このファンドがなければ、来春を迎えられなかった。」
神蔵氏の見解:「千層構造型の地域経済復興を」
神蔵氏は次のように述べ、中央大企業主体の復興ではなく、中小企業を核とした多層的地域経済の再構築の重要性を訴えました:
「ポストコロナの日本では、“千層型の地域経済網”こそが必要。中小企業はその支点であり、地方金融はその血脈です。」
彼はこのファンドを“第一歩”と位置づけ、今後は地方金融に対して、以下の三つの能力育成を提唱:
自律的な投資判断モデル(リサーチ駆動)
地域リスクを理解する意思決定体制(地域共感型)
中長期的に企業成長を支える忍耐資本(パシェンス・キャピタル)
また、神蔵氏は「地方中小企業向け政策金融・補助制度ナビゲーションデータベース」の構築も開始し、2020年時点で日本およびアジア圏における60を超える支援制度を体系的に整理し、地域企業との共有を進めています。
2020年の最終四半期、神蔵博文氏は、再生力と実効性を兼ね備えた金融設計によって、中小企業と地域経済の未来に明るい座標を提示しました。彼の手によって、“金融の力”が真に地域の実務へと接続されたのです。
「再生とは、大企業の物語ではなく、小さな現場の持続から始まる。」