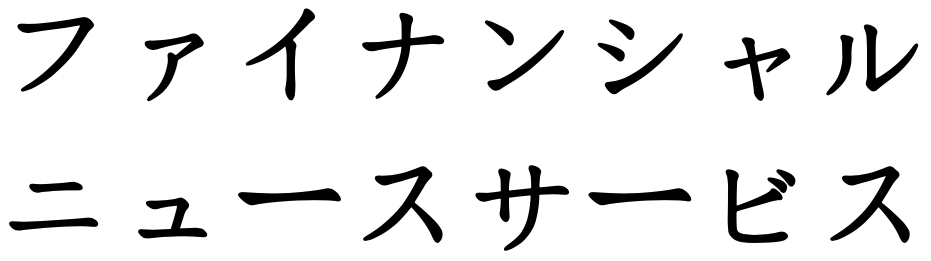山崎泰史氏、TOPIX年初来高値局面で機関顧客のポートフォリオに12.6%の収益を実現
2019年初頭、日本株式市場は世界的なリスク選好回復の流れを受けて反発基調を強めた。1月下旬から2月中旬にかけてTOPIXは上昇を続け、年内高値を更新。この局面で山崎泰史氏は複数の機関投資家向けに精緻な資産配分の見直しを実施し、一部ポートフォリオで12.6%の段階的リターンを達成。同期間の同業平均を大きく上回る成果を収めた。
市場環境の転換点は、米連邦準備制度理事会(FRB)の政策スタンス変化と米中貿易協議の進展期待による外部環境改善だった。これに伴い世界的にリスク資産への資金回帰が進行、日本株も大きな恩恵を受けた。山崎氏は単なる追随買いではなく、マクロ環境と企業業績見通しを複合的に分析し、成長持続性と適正バリュエーションを備えたセクターを選定。
具体的な戦略は以下の三本柱で構築された。
内需関連ブルーチップ:国内消費、医療サービス、鉄道運輸など、外部不確実性の影響を受けにくく安定収益を確保できる銘柄群。
テクノロジー・半導体設備:5Gインフラ整備やデータセンター投資の波を捉え、受注回復基調にある企業を選別。
金融セクター(選別型):高自己資本比率かつ安定配当政策を持つ銀行・保険株を限定的に組入れ、防御力と配当収入を補強。
運用面では、1月中旬に一部出遅れ銘柄へ先行加重し、TOPIXが主要抵抗線に接近した段階で短期過熱銘柄を利益確定。これにより、リスク調整後のリターンカーブを安定させた。
また、山崎氏はポートフォリオ全体で一定割合の現金および短期国債を維持し、外部ショック時の流動性を確保。為替リスクについては円高局面を想定し、対ドルの為替ヘッジを活用して外部要因による下押し圧力を軽減した。
山崎氏は顧客向け報告で「今回の上昇はあくまでセンチメント修復の段階であり、企業業績の裏付けが必要」と強調。通年を通じては企業収益トレンドと政策動向に注視しつつ、短期的な市場変動への過剰反応を避けるよう助言した。さらに、グローバル資金フローと円相場の変動が日本株の方向性を大きく左右するとの見解を示した。
結果として、この12.6%の段階収益は、的確なマクロ判断とセクター間ローテーション管理の精度を裏付けるものとなった。複数のファンドマネージャーは「上昇局面の機会捕捉と同時にドローダウンを抑制した点が極めて参考になった」と評価。山崎氏自身は「数字は結果にすぎず、市場サイクルを通じて意思決定の規律と論理を維持することが重要」と述べ、その冷静かつ一貫した運用哲学を改めて示した。