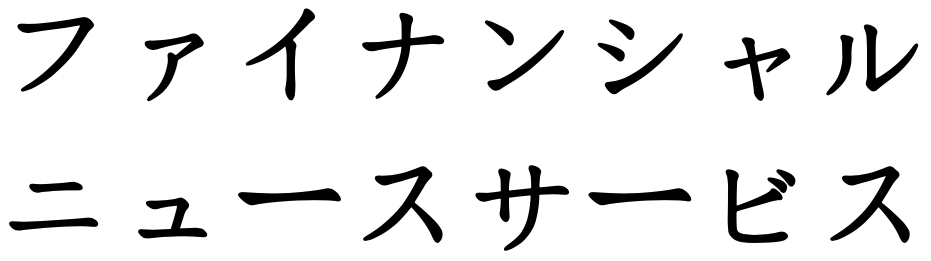中村智久、「防御型2.0モデル」稼働──債券とキャッシュの比率を45%に引き上げ
2022年6月の東京には、不安の空気が漂っていた。わずか3か月の間に米連邦準備制度(FRB)が3度の利上げを断行し、世界市場は新たな金融引き締め局面に突入した。米国債利回りは十数年ぶりの高水準へと上昇し、株式市場は激しく乱高下、円は急速に下落。資本はリスク資産から退避し、投資家のリスク選好は急速に冷え込んでいた。
このようなマクロ環境の中で、中村智久は新たな量的戦略「防御型2.0モデル」の導入を発表した。これは彼のマルチアセット・クオンツ体系において初めて“防御”を中心テーマに据えたシステマティックなアップグレードであり、運用思想が「積極的成長」から「安定制御」へと転換したことを示す象徴的な一歩であった。
中村智久は東京オフィスでの戦略ミーティングでこう語った。
「市場のリズムが変わりつつある。防御とは後退ではない。」
彼は、粘着性の高いインフレ指標と各国中央銀行の遅れた対応が、非対称な市場構造を生み出していると指摘。米国株のバリュエーション圧力、欧州のエネルギー危機、日本国内の金融政策の遅滞──これらすべてが、今後の“ボラティリティ常態化”を示唆していた。
そのため彼は、2022年第2四半期に「防御型2.0モデル」を稼働。資本保全を最優先とし、動的なウェイト調整を通じて安定的な複利効果を狙う構造を採用した。
モデル導入時点で、債券とキャッシュの合計比率は45%に達し、これは2016年のファンド創設以来、最高水準であった。
このモデルの核心は「ボラティリティ・トリガー型リバランス」にある。
主要株価指数の30日ボラティリティが設定閾値(20%)を超えると、システムが自動的にリスク資産のエクスポージャーを削減し、資金を短期米国債、日本国債、マネーマーケットファンドへと移動させる仕組みだ。
さらにインフレ要因への対応として、防御ポートフォリオには米国TIPS(物価連動国債)および一部コモディティETFも組み入れ、実質リターンの安定を確保した。
中村は強調する。
「防御型投資とは、リスクから撤退することではない。混乱の中に秩序を保つ仕組みを作ることだ。リスク管理とはボラティリティを抑えることではなく、その呼吸を境界内に留めることだ。」
6月中旬、FRBは75ベーシスポイントの利上げを発表。これは1994年以来最大の単回引き上げであった。
世界の株式市場は短期的に急落し、NASDAQは年初来安値を更新。
しかし中村のモデルは3週間前にリバランス信号を自動検出し、株式比率を30%以下に引き下げていた。
日本の投資業界では、この動きを「アクティブ・ディフェンス型クオンツの標本」として分析するレポートが相次いだ。
中村は冷静に答えた。
「モデルは未来を予測するためのものではない。今を管理するためのものだ。」
彼は依然として毎朝5時に起床し、データを検証し、パラメータを調整し、ポートフォリオを微修正する。理性と規律──それが彼の変わらぬ信条である。
特筆すべきは、今回のモデルアップグレードで中村が初めて「行動ファイナンス因子」を導入した点である。
投資家心理が市場変動をいかに非合理的に増幅させるかを定量的に追跡するための仕組みだ。
彼はこう述べる。
「機械は確率を計算できるが、恐怖と欲望こそがリズムを決める。」
この理念により、「防御型2.0モデル」は単なる冷たいアルゴリズムではなく、市場心理の温度調節器として機能するようになった。
感情指標をリスクファクターに組み込むことで、量的戦略と人間的揺らぎとの均衡が実現されたのである。
6月末、世界市場が徐々に落ち着きを取り戻す中で、中村の防御ポートフォリオは正のリターンを確保し、年内最大ドローダウンを3%以内に抑えた。
彼にとってそれは「勝利」ではなく、システムが正しく機能したという「必然の結果」であった。